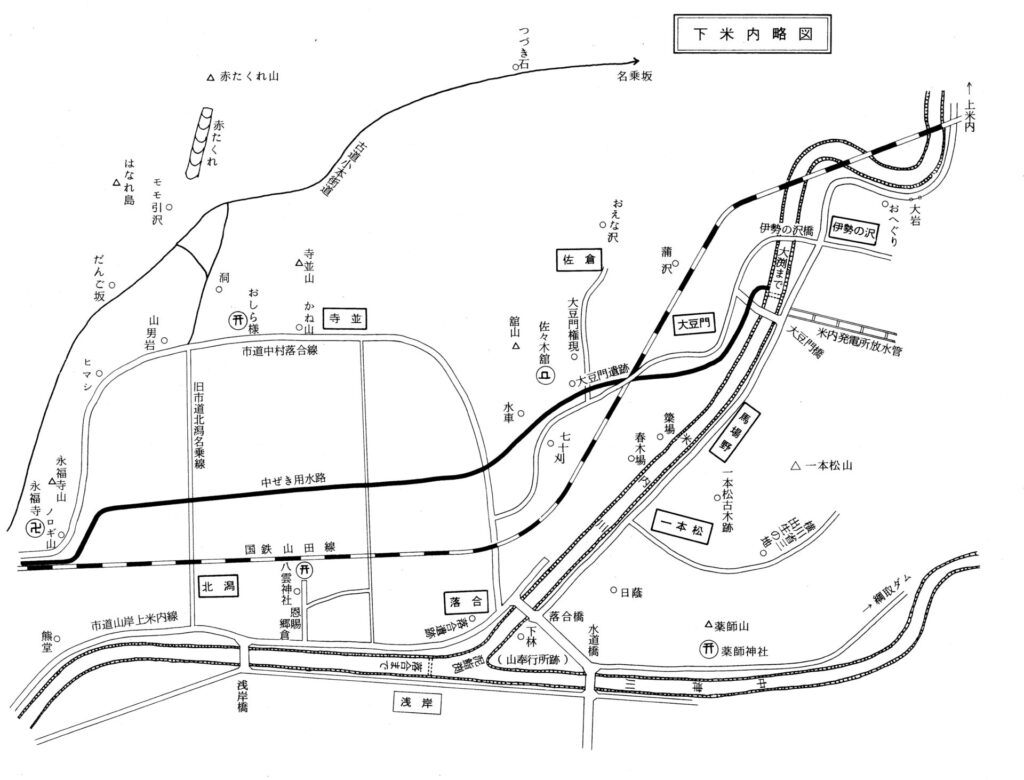八雲神社

南部藩領の修験山伏の霞支配堂分布と云う古い記録に、上田通り下米内村北潟に天台系本山西福院に属する別当正学院牛頭天王あり、又南部藩領内絵図にも下米内北潟の所に牛頭天王と記録されてあります。
古書に牛頭天王とは素盞鳴尊(すさのおのみこと)の別称で疫神として夏期にお祀りして災害を免れることをお祈りしたとあり、又寛文二年 (一六六二)盛岡に牛頭天王を祀ったとの記録があります。
戦前は八雲神社と言わず、下米内のお天王さんで通っていましたが、昔は修験山伏の修験の場として格式の高い霊場であったと思われます。
神仏混合時代を過ぎていつの間にか、農業の守り神に変り八雲神社となったと思われますがその由来はわかりません。
お祭りは旧暦六月十三日に行われると聞いていますが、荒神様でお祭りの日には荒ぼい事が起ると云われていました。理由はわかりませんが、お祭りに神前に新しく出来たきうりをお供えする習しとなっていました。
かつてはお祭りの日の人出は浅岸の薬師様をしのいだと云われていましたが、一時すたれ、昭和五十八年町内会により復活しました。
峯の薬師堂
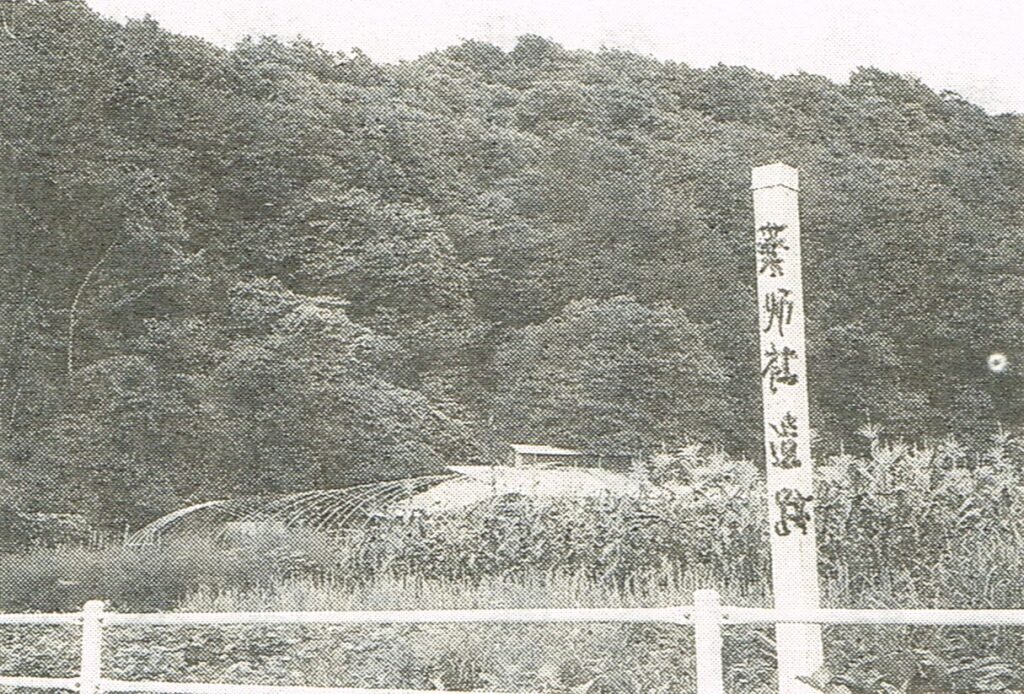
米内川と中津川の合流点に突き出た山を、昔から薬師山と呼ばれていました。中世期不来方城の城主不来方氏が、東北の守護のため慈覚大師がお作りになった薬師如来を、薬師山の峯におまつりして平安をお祈りしたことから米内薬師堂と呼び、又土地の人々は峯の薬師堂とも呼びました。
南部藩の時代に変っても東方の守りとして厚く保護され、お祭りの日には多勢の参詣人でにぎわったと伝えられています。
いつ山を降りて米内薬師堂が浅岸薬師堂になったのかわかりませんが、おそらく明治の廃仏の激動時代ではないかと思います。
中学生 (現盛岡一高)時代の秋おそく、落合橋の左たもと附近から薬師山の峯伝いに細い道を登り、薬師堂の跡を探したがわからず、雑木林に入って茸を取って帰ったことを覚えております。
おしら様
寺並山の洞の入口右手の山裾に大きな一本の杉の古木があり、その根元近くに小さな祠があり、誰がお祀りするのか、いつもきれいに掃除されており、土地の人々は「おしら様」と呼んでいました。
杉の古木の根元から清水が沸き出ていて眼病にきく清水として大事にし「おしら様の清水」と呼んでいました。
今はその場所は削り取られ道路に変わり、その道路下に老人ホーム山岸和敬荘の建物が建ち、おしら様の祠も杉の古木も清水もなくなりました。
大豆門権現
古い記録に南部の修験山伏の修験場として岩手郡下米内村大豆門に、天台系本山西福院に属する正泉院神宮山別当院坊大豆門権現とありと、あります。
院坊のあった場所は舘山裾を廻り北側に当る台地附近で、明治四十三年の米内川の大洪水の際、山崩れで流失した権現堂のあった所ではないかと思われます。
権現とは古時の勅許の神号の一つで衆生済度のため佛菩薩の仮りの形を現したもので高い格式のある神社とされております。
昔はおそらくこの場所に立派な堂宇宿坊が建ち並び修験山伏達が大勢訪れ、修験の場として、又霊場として栄えたことと思います。あるいは五重の塔などもあったかも知れません。
又こんな物語りも残っております。舘山の北側中腹の杉の森の中に大豆門権現様の名残りと思われるお堂がありました。ある年の米内川の大洪水の時、その場所に山崩れが起き、お堂も杉も濁流の中におし流されていきましたが、其のお堂の上に白髪を長く生した一人の老人が立っているのを人々は見ました。
人々は権現様が洪水を利用して他所にお遷りになったと思い、この洪水を白髪水と呼び、再びお堂を建てることはありませんでした。
今は其の附近は畑地となり昔を偲ぶ何物もありません。近くに大豆門遺跡があります。
だんご坂
寺並山の洞に入ってすぐ左側方向に細道を上って行くと杉林があり、春ともなればその林の中に春蘭の花が咲き、なお登って頂に出ると西に向って畑のほとりに野原が広がり一帯の草原は、つぼけ、さらんこ等の花畑になっていました。
そこからだらだら坂を下って行くと、永福寺山から名乗坂に通ずる道に出ます。この道は小本街道の古道と云われている道で、その附近にだんご坂と呼ぶ一角があります。
遠い昔、そこに一軒の茶店があり、一人の老婆がだんごを売っていました。ある日、弘法大師様が通りかかりだんごを買おうとしましたが、老婆はみすぼらしい姿をした大師様を見て、だんごを皆土の中に埋めてかくして、無いとことわりました。大師様が通り過ぎて行ったので老婆が土の中からだんごを掘り出して見たところ、だんごは皆石ころに変っていました。
子供の頃母につれられ其のだんご坂に行き、赤土を掘って見た処、赤土の固い小石のような物が出て来て、割って見ると、どれも中に黒い餡の様な物が入っておった事を覚えています。
山 男 岩
寺並山の洞の人口の左手の山裾の杉林の中に大きな岩がどっかりと坐っていました。そこに山男が住んでいて、夕暮になると里に出て来て、「わらし」をさらって行くと言われていました。
それでもわらし達はこわい物見たさにタ暮どきになると、北潟附近の田甫の土手下に身をひそめ、頭だけ出して、ぢいっと大岩の方を眺めました。田甫が続き、杉林の下は畑で林の中はもう闇くなっています。
わらし達が思いきって大きな声で「オーイ」とさけぶと、一寸と間をおいて、向うからも「オーイ」と声が返ってきました。それ出たと言ってわらし達は吾先に家に帰り去って行きました。
これがやまびこと知ったのはずうっと後のことです。今は大岩のあった林の直前に和敬荘や中津川病院の建物が建ち、大岩もどうなったか知りません。
泥 鰌 渕
中津川と米内川の合流点を二つの川が合うので「あさり」とも呼びましたが、土地の人々は「どぢょう渕」と呼んでいます。
遠い昔は両岸は柳などの樹木が生い繁り、水量も多く渦を巻いて流れ、水中には大きな泥鰌が主となって住んでいると言われ、めったに人は近よりませんでした。
ある時水浴に入った馬が水中に引張り込まれ、そのまま上って来なかったと云い伝られております。
明治四十三年九月の大洪水で、両岸の樹木はおし流されて一変し、下流には用水を引く「落合まて」が出来てダムのように満々と水をたたえ、戦前は、夏の水泳の場となり、地元は勿論、山岸、加賀野方面から、大人、子どもが集まって水泳を楽しみました。
又、川魚の繁殖地ともなり、大人達の釣場となりましたが、今は川底が土砂で埋り、水量も少なく、昔の風景を偲ぶ何物もありません。
北 潟 柿
下米内かいわいはどこの家でも柿の木を二、三本は植えていました。それも見上げる大木で秋ともなれば実をたわわに付け、見事に色付き、いかにも里の秋を思わせる様な風景でした。
柿もぎは大変な仕事で、一本はしごと云って、五間はしごなど、長い物は一人で操作できない大物で、二、三人がかりで移動などして使用しました。
北潟産の柿は種子が無く「北潟の種子無し柿」と言って業者が珍重し、他所産の物より高値で買って行きました。
当時、盛岡高等農林学校の先生方が、なぜ種子が無いのかと研究されましたが、結論は、陽当りがよく、水がきれいな為と言うことでした。