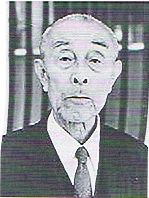葛精一氏(鳥類学者)
明治27年(1894)~昭和59年(1984)
盛岡高等農林学校(現岩手大学農学部)卒業
農商務省鳥獣調査室に勤務し、農商務省猟政調査課長、森林保護室長、林野庁調査官等を歴任し鳥類研究、保護に従事する。
第一回日本鳥学賞受賞(1956年)
岩手日報文化賞受賞(1971年)
盛岡市の市政功労者表彰(1976年)
生家は下米内宇佐倉(葛 博伝には大豆門35とある)である。ちょうど、第二大豆門踏切の北側の箇所で、現在は廃屋同然となっている茅葺の建物が幼少期を過ごした所である。現在でもそうであるが、周囲は自然に囲まれた環境であり、幼少時より野鳥に親しみ、その種類の多さ、多様さ、鳴き声の美しさ、習性等に興味を抱いていった。小学生時代には野鳥の生態を知りつくし、鳥類研究の第一人者であった内田清之助博士もたびたび葛少年を訪れたほどで、内田氏に博士論文の資料を提供したりしたという。のちに内田氏の指導を受け、野鳥研究の道を歩むこととなる。
野鳥の食性調査では、従来害鳥とされていたスズメとカケスの評価を高めた。スズメについては農林業上の有害昆生を啄(ついば)むことを明らかにし、カケスについては餌の大部分が有害昆虫類と森林の有害植物であることを証明し、狩猟鳥から除外させた。
また、渡り鳥の調査も行い、調査方法で鳥の足にアルミ管の標識を付けることを考案し、効率的調査に貢献した。
昭和33年(1958)に世界鳥類保護連盟総会に政府代表として出席、昭和35年(1960)には東京での国際鳥類保護会議にオブザーバーとして出席するなど、国内外ともに野鳥研究の第一人者として活躍した。
また、皇居内の野鳥保護や昭和天皇の鳥類研究のお相手、当時の皇太子殿下の狩猟のご指導役を務めたことでも知られている。
退官後は郷里盛岡に戻り、国や県の依頼により岩手に生息する野生鳥獣の生態調査や後進の指導にあたり、本県の鳥獣保護に貢献し、岩手日報にも「野鳥の四季」を連載して啓蒙活動を行った。
なお、精一の兄に葛 博がいる。葛 博は岩手県職員として稗貫郡長を務めた当時、宮沢賢治と親交があった。宮沢賢治は盛岡中学時代に精一と同級であった。
葛 博はまた、ダリアの栽培研究家としても知られている。
参考文献:盛岡市公式ホームページ